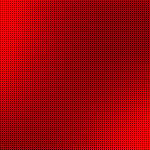その日の夜八時頃、仕事から帰ってマンションの入り口にある郵便受けを開けると、中に二つの眼球が浮かんでいた。正確にはきちんと開けたわけではなくて、ただ中身が入っているかどうか投入口から簡単に確認しただけだったのだが。僕はその眼球と、たぶん十秒くらい向き合っていたのではないかと思う。僕は投入口を指で押さえながらその目をじっと見つめ、一方でその目は僕をじっと見つめていた。我々の間には、奇妙にしんとした空気が漂っていた。
「いや、どうも、失礼しています」と彼は言った。
「失礼しているって、一体どうしてそんなところに入り込んでいるんです?」と僕は聞いた。
「いや、なんだかここは居心地が良くってね」と彼は言った。
「そんな狭いところが、居心地が良い?」
僕は改めて状況を確認してみた。その郵便受けはごく普通の郵便受けで、どう考えても人間が入り込めるスペースは無い。というか人間の頭だって入らないだろう。僕は幻覚を見ているのだろうか?
「いや、幻覚なんかじゃありませんよ」とそこで彼は言った。「私はちゃんとここにいますし、それが見えている方がまともなんです」
「そんなところで一体何をしているんです」と気を取り直して僕は聞いた。
「手紙を待っているんですよ」と彼は言った。「だってそれ以外ないじゃありませんか」
「手紙?一体誰からの手紙なんです?」
彼は名前を言った。それは僕がずっと手紙を待っているある女性の名前だった。
「なんであなたが彼女のことを知っているんです」
「だってあなたずいぶん長く彼女からの返事を待っているでしょう」と彼は言った。「そういう心持は、郵便受けの中にちゃんと残っているんです。今か今かと待っているその期待が、ひしひしとこちらに伝わって来るんですよ」
僕は認めた。「ええ、確かにここ最近ずっと彼女からの手紙を待っています。それは僕にとってはとても大事なことなんです」
「でもこのEメールとソーシャルメディアの時代に手紙とは、あなたも古風ですね」と彼は言った。
「手で書いた方が、気持ちがより伝わると思ったんです」と僕は言った。
「でもそういうのは彼女にとっては重荷に感じることだったのかもしれない」と彼は言った。
「そうでしょうか」と僕は不安になって聞いた。
「いや、たぶん大丈夫でしょう」と彼は言った。「あなたはそういう人だ。だから私はあなたが好きなんです。彼女はきっと返事をよこすでしょう」
それを聞くと僕はなぜかほっとしてしまった。「どうもありがとう。そうだ、ガムでも食べませんか?」。そう言って僕はミント味のガムを郵便受けの中に差し入れた。
「ああ、これはどうも」と彼は言った。「包み紙は取ってもらった方がいいですね・・・ああ、どうも」
すると中からくちゃくちゃという大きな音が聞こえてきた。「いや、くちゃくちゃ、ガムなんて、くちゃくちゃ、ずいぶん久しぶりですよ、くちゃくちゃ」
「それで」と僕は改めて聞いた。「あなたはなんでそんなところにいるんです」
「私はね、ずうっとここに住んでいたんです」と彼は言った。どうやらガムは飲み込んでしまったようだった。
「ずうっと?」と僕は言った。
「ええ、そうです」と彼は言った。「あなたのガス料金やら、水道料金やら、クレジットカードの支払い料金まで、そういうのも全部見てきました」
「それで、なんで今姿を現したんです」
「それはあなたに警告しなければならないと思ったからです」と彼は言った。心持その口調が重みを増したような気がした。「あなたは今ある種の危機にいます。精神的な危機です」
「精神的な危機」と僕は言った。
「あなたは彼女からの返事に全ての期待をかけてしまっているようだ」と彼は言った。
「何も彼女に対してなにもかもを期待しているというわけじゃ・・・」と僕は言いかけたのだが、彼が素早く遮った。
「いや、なにもかもを期待しているんです」と彼は言った。「彼女があなたのことをどう思っているにせよ、あなたは彼女にそんなことを期待するべきじゃないんです。あなたは自分自身に期待しなければならないんです」
「それは自分でも分かってはいます」と僕は言った。「でも時々自分の足場というものがどこにも無いと感じるんです。そして何かにすがりつきたくなるんです。溺れている人が藁を掴むように」
「いいですか」と彼は少し口調を強めて言った。「あなたはまだ溺れてなんかいない。あなたは本当はもっと強い人なんです。自分でそれを認めるのが怖いだけなんだ」
僕は何も言い返すことができなかった。
「私はずっとここからあなたのことを見て来ました」と彼は言った。「郵便受けに長くいるとね、雰囲気で色んなことが分かるようになってきます。あなたがどんな風に郵便受けを開けるか、どんな顔で中身を見るか、それによってあなたのことが良く分かるようになってきます。そこで言いますがね、あなたは今、一歩先に踏み出さなければいけない地点に来ています。思いきった一歩を」
「それは具体的にどういう一歩なんでしょう」と僕は聞いた。
「具体的なことはあなたが自分で考えるしかありません。結局のところ私はしがない居候に過ぎない。でもそれについて私にもひとつできることがある」
「あなたに?」
「そうです」と言って彼は頷いた(ような気配があった)。そして「この中に指を入れてくれませんか」と言った。
「指?」と僕は聞いた。「どの指です」
「全部です」と彼は言った。「左手の指を全部入れてください」
僕は良く分からないまま左手の指全部を投入口から差し入れた。
「そう・・・それで良い」と言う声が聞こえ、そして次の瞬間、激しい痛みが僕の左手を刺し貫いた。
「痛っ」と言って手をひっこめると、左手の指全部から血が流れ出していた。そこには信じられないくらい深い歯型が付いていた。
「何をするんです」と僕は怒って言った。
「おまじないです」と彼は何でもなさそうに言った。「次はあなたの番です」
すると投入口の蓋が空いて、そこから手が差し出された。若いのか、年を取っているのか見分けのつかない手だった。「次はあなたが噛む番です」
「どうして僕がそんなことを」と僕は言ったのだが、彼は断固とした口調で言った。「早く、誰かがやって来て見られてしまうかもしれない」
そこで仕方なく僕はその指を噛むことにした。知らない人間の指を口に入れるというのは、そんなに気持ちの良いことではない。僕はごく軽く噛んだ。
「もっと強く」と彼は言った。「血が滲むくらい強く」
そんなに強く噛んで欲しいんなら、と僕は思った。望み通りにしてやろうじゃないか。
僕は力の限りその指を噛んだ。彼の指の皮膚が裂け、そこから血が滲むのが分かった。僕は舌に彼の血の味を感じた。僕が口を離すと、彼は満足したように言った。「そうです、それでいい」
僕は額に汗をかいていた。そして周りを見回した。こんなところを人に見られたら、一体何と説明すればいいんだろう?すると彼が言った。
「最後に握手をしよう」。そして血のにじんだ手をパタパタと下の郵便受けに打ちつけた。
僕はさっき彼に噛まれた左手で、さっき自分が噛んだ彼の手を握った。お互いの血が我々の掌の中で混じり合った。
「いいかい」と彼は言った。急に口調がくだけてきていた。「この感覚を覚えておくんだ。大事なのは血と痛みなんだ。その先に真の喜びがある。君はきっといずれきちんと生きることができるようになる。今はまだ十分な自信が無いっていうだけなんだ。だからいつまでも郵便受けに何かを期待するのはやめて、自分自身に期待しなくてはならない。今度また生半可な気持ちでやってきたら、同じように噛みついてやるからな」
僕は自分の左手を眺めていた。そこには彼の血と、僕の血が混ざり合って赤い跡を残していた。
「今度あなたに手紙を書きますよ」とふと思いついて僕は言った。「受け取ってくれますか」
「もちろん」と彼は言った。「首を長くして待っているよ」
僕はなんだかぼおっとしてしまって、しばらく自分の手を眺めたままそこに立ちつくしていた。部屋に帰る前にダイヤルキーを回して郵便受けの扉をきちんと開けてみたのだが、そこはきれいに空っぽだった。僕はもう一枚包み紙から出したミントガムをそこに置いて、それからひとつ深呼吸をすると、元いた自分の人生へと帰って行った。