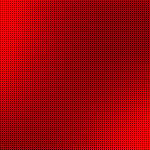彼女はもう長年魔女をやっていて、そのとき大きな鍋の中身を木べらでかき回しているところだった。その中身が何なのかは分からなかったが、辺りにはなかなか良い匂いが漂っていた。
「蝦蟇の胆嚢とか、トカゲの尻尾とか、そういうのは入れないんですか?」と僕は聞いた。
「蝦蟇の胆嚢?なんでそんなもの入れなきゃならないのよ」と彼女は驚いて言った。
「だってあなた魔女なんでしょう」
「いくら魔女だってそんなもの入れないわよ」と彼女は言った。「今は二十一世紀なのよ。あなた頭が四百年くらい古いんじゃないの?」
「だって『マクベス』でそういうの読んだ気がしたから」
「ああ、あの三人組の魔女ね」と彼女は言った。「あれ私の大叔母なのよ」
「三人とも?」
「そう、三人とも」
『マクベス』に出て来る魔女が大叔母ということは、彼女は今一体何歳なのだろう、と僕は思った。でも実際に年齢を尋ねたりはしなかった。女性に年齢を尋ねたりするのは、僕のポリシーに反する。
「じゃあその鍋には一体何が入っているんですか」と僕は聞いた。
「そりゃあ赤ワインとか、ローリエとか、玉ねぎとかトマトとか牛筋肉とか、そういうものよ」と彼女は言った。
「それじゃあ普通の煮込み料理と何も変わらないじゃないですか」と僕は驚いて言った。
「そうよ。当たり前じゃない。あなた一体何を期待していたの?」
「だってあなたは魔女だって聞いてきたから」
「そりゃあ確かに私は魔女だけど」と彼女は言った。「本当に大事なのはね、心持ちなのよ。もし私が憎しみを込めて作ったら、この料理は致死的な力を持つ。もし私が愛を込めて作ったら、この料理は人々を救う。蝦蟇とかトカゲとかっていうのは、言うなれば一種のパフォーマンスなの。かつてそういうのが必要とされた時代があったのよ」
「じゃあ今はどんな気持ちを込めてその料理を作っているんですか?」
「教えてあげない」と彼女は意地悪く言った。「食べてみてからのお楽しみ」
僕は友人に紹介されてその魔女の家を訪ねた。「魔女の家」と聞いたとき僕は怪しげな調度品に囲まれてぼろぼろに朽ち果てたいかにもという家を想像していたのだが、実際にはそこは小奇麗な住宅街に並んだ小奇麗な家のひとつに過ぎなかった。そして呼び鈴を押して中に入ってみると、ごく普通の中年女性が、ごく普通に煮込み料理をしていたというわけだ。
「それで、どんな用があってここに来たわけ?」と鍋をかき回しながら彼女は聞いた。
「実はひとつお願いがありまして」と僕は言った。
「一体どんなお願いかしら」
僕は彼女に近寄り、そっと耳打ちをした。部屋には僕らのほか誰もいなかったのだが、なんとなくそうした方が良いような気がしたのだ。僕のお願いを聞くと彼女ははっと息を飲んだ。
「あなた本気なの?」と彼女は言った。
「本気です」と僕は言った。
彼女は真剣な目で僕を見つめていた。そして言った。
「良い?良く聞いてね。それには命がかかるわよ」
「構いません」と僕はきっぱりと言った。
彼女は木べらを動かしながら天井を見上げ、何かを思い出していた。まるで天井にその何かの痕跡があるみたいに。
「昔あなたみたいな人がいたわ」とやがて彼女は静かに言った。
「あれは戦争が始まってすぐの頃だった。あのときも私は『命がかかるけどいいか』って聞いたの。そしたら彼は言った。『どうせ僕はもうすぐ前線に送られるんです。もうとっくに死を覚悟しています。命をかけるくらい全然構いません』って。でも彼は耐えられなかった。すぐに頭がおかしくなってしまったの。まあそのおかげで前線には送られずに済んだけど、結局残りの人生を精神病院のベッドの上で過ごす羽目になった。ちなみに彼はドイツ人で、戦争というのは第一次世界大戦のことなんだけど」
彼女はそこでおたまを使って鍋の中身を少しだけ掬い取り、味見をした。そしてほんの少し塩を足した。「あなたそれでもやるつもり?」
「もう心は決まっています」と僕は言った。
彼女は一度深い溜息をつき、言った。「それじゃあ裏の物置から色々と必要なものを持って来るから、その間あなたはこれを食べていなさい。あなたがこれからやろうとしているようなことにはね、栄養のある食事が一番なのよ。みんなはそうは思わないみたいだけど。みんなはね、熱意とか、意気込みさえあればなんとかなると思っているのよ。でもそれだけじゃ駄目なの。全然駄目。栄養を摂らないと力なんて出せないんだから」
彼女は鍋の中身を真っ白い深皿に分け、スプーンを添えて僕の前に置いた。そして「しっかり食べなさい」と言い、裏口から外に出て行った。彼女が出て行ってしまうと、部屋の中は急にしんとして、ひどく静かになってしまった。ずっと遠くの方で車の走る音が聞こえた。僕は目の前に置かれた煮込み料理をスプーンで掬い、一口食べた。香草の香りが、新鮮なトマトの酸味とよく合っていた。僕は目をつぶり、良く味わいながらゆっくりとその料理を食べ進めていった。彼女がそこに何を込めたにせよ、それは僕の中の一番深いところにしっかりと染み込んでいった。