朝起きると私はワニになっていた。といっても姿形がワニになったわけではない。あくまで意識がワニになったということだ。もちろん今このように回想できていることからして、100パーセント完全なワニになったというわけではないと思う。でも95パーセントまではワニになっていた。
それはおそらくアマゾン川流域のワニだった。私はひしひしとそれを感じ取っていた。耳の奥にあの大河の滔々たる水の音が聞こえてきた。異国のサルの鳴き声が、かん高く空に響いた。
しかし実際に私がいるのは、東京都郊外の、六畳一間の狭いアパートの一室だった。ワニとしての私はそのギャップにひどく不愉快な気分になった。あまりにも不愉快だったので、着ていたパジャマの袖を歯で噛みちぎってしまったくらいだ。
広大なアマゾンからやってくると、ここはあまりにも不自然で、狭すぎた。私はかろうじて残った5パーセント分の人間の意識をかき集めて、いつものスーツ姿に着替えた。それは初冬の出来事で、外はずいぶん寒かったのだが、そんなことを気にしている余裕はなかった。私は靴を履き(幸いそれはワニ皮ではなかった)、そのままの勢いで外に出た。
時刻は午前8時前で、外には登校途中の小学生たちの姿が見えた。私はひどく腹を減らしていて、その無邪気な姿を見ると、とたんに口の中に大量の唾液が湧いてきた。しかし横断歩道のところには、黄色い旗を持った登校ボランティアの老人の姿が見える。もしここで小学生に噛みついたりしたら、たちどころに警察に通報されてしまうだろう。
しかしこのように都会にいることへのフラストレーションはあまりにも強く、耐え難かったため、私は何かに噛みつかずにはいられなかった。そこで手近にある街路樹に噛みついた。何という名前の木かも分からない。おそらくアマゾンには生えていない種類のものだろう。しかしそんなことに構っている暇はなかった。私の歯、そして顎は、何か強く噛むことのできる対象を求めていたのだ。
木に抱きつき、思い切り噛みつくと、私の意識はあの広大なアマゾンに一瞬だけ戻った。広い水の流れ、鮮やかに光る鳥の翼。しかし樹液の苦い味が口に広がり、途端にこの世界に連れ戻されることになった。コンクリートで囲まれたこの灰色の街に。これはあまり美味しくない木だ、と私は思った。都会に生えている木なんて、しょせんこんなものさ。
私が噛みついているのを見たらしい車のドライバーが、ものすごく不思議そうな顔をしてこちらを見ていた。40代後半くらいの女性だったが、私は軽く会釈して、何事もなかったかのようにその場を離れた。まあ彼女だっていい歳をした大人なのだから、成人男性には、ときにこういう衝動が湧くことをきっと理解してくれるだろう。
私は木のほかに何か噛みつけるものがないだろうかとあたりを見回した。しかしあの広大なアマゾンからやって来てみると、そこにあるのは何もかも味気ない人工物にしか見えなかった。信号機、錆びた歩道橋、アスファルト、コンビニの壁。どれもうまく噛みつけそうにない。
と、そのとき歩道橋の手すりに一羽のスズメが止まっているのが見えた。それは私の狩猟本能を刺激した。もちろんそこに着くまでそいつがずっとそこに止まっているという保証はない。でも試してみる価値はあるだろう。
私はゆっくりと、音を立てずに歩道橋を上り、そのスズメに近づいた。それは純粋無垢な鳴き声を上げ、ぴょんぴょんと手すりの上を移動していた。しかしまだどこかに飛び立とうとはしない。私の餓えた胃袋は、今か今かと獲物がやってくるのを待っていた。じわりと唾液が湧いた。私は辛抱強くゆっくりと近づき(これはワニの得意技だ)、やがてそのすぐ背後にまでやって来た・・・。
しかしそのとき反対側から一人の小学生の男児がやって来て、その鳥に掴みかかろうとした。もちろん手は空を切り、鳥はどこかに飛んで行ってしまった。またあの純粋無垢な鳴き声を残して。私は怒りと餓えのためにその小学生をまじまじと睨みつけた。こいつは私の貴重な食料を奪ってしまったのだ。自分が何をしたのかも知らずに。
彼は不思議そうな顔をして私のことを見つめていた。でもやがて私が実はワニであることに気付いたらしかった。小さな子どもというのは、そういう点に関してはとても感覚が鋭い。大人のように見た目に簡単に騙されたりはしない。そして幸か不幸か、私が彼を喰ってしまう前に、一目散に走り去っていった。
あとに残されたのは錆びた歩道橋の手すりと、私の餓えた胃袋だけだった。私はどうしてもその手すりを噛まないわけにはいかなかった。あまり衛生的とは言えないが、かといって今はこれ以外に噛むものはない。私は目に涙すら浮かべていたと思う。このように生を受け、せっかく立派な顎と肉体を持っているのに、噛むべきものが見つからないなんて。私の目の下では、通勤途中の車が列を成してどこかに進んでいた。トヨタプリウス。ホンダフィット。フォルクスワーゲンの小さいやつ。あと何だかよく分からない車たち。それを見るともなく見ていると、だんだん一つの川の流れのようにも見えてきた。もちろんあの広大なアマゾンには比すべくもないが、それでも流れは流れだ。その光景は私の心に何かをもたらした。何か自然で、肯定的なものだ。そのとき肌に突然風を感じた。気持ちのいい風だ。それはまさにアマゾンから吹いてきた風だった。私にはそれが分かった。地球の裏側から、この東京都郊外のいささか錆びれた街にまで、はるばるこの私のためだけにやって来たのだ。
私はいまだ手すりに噛みつきながら、その風を全身に感じ取っていた。そしてこう思った。私にとってのアマゾンは、すでに失われてしまったのだと。そう思うと涙が落ち、下を走る何だかよく分からない車の上に落ちた。そしてそのままどこかへと運ばれ(きっとドライバーの職場の駐車場だろう)やがて蒸発していった。私はたった一人そこに取り残され、手すりにしがみつき続けていた。そしてもうこの世に噛みつくべき価値のあるものは何一つ存在しないのだ、と感じ取っていた。そのとき誰かが背中を叩いた。
見るとそれは一人の女の子だった。ランドセルを背負い、黄色い帽子を被っている。見たところさっきの男児と同じくらいの歳に見える。小学校1年生か、2年生くらいだ。彼女はたった一人でそこにいて、そこにしがみつく私をじっと見つめていた。その時点では私はもう子どもを食べたいとは思えなくなっていたので、早くいなくなってくれないか、と思っていただけだった。でも彼女はいなくならなかった。そこにいて、その恐ろしく澄んだ目でじっと私を見つめ続けていた。
そのとき気付いたのだが、彼女は人間ではなかった。いや、もちろん姿形は人間なのだが、その中には――その中のおそらく95パーセントは――一匹のチンパンジーだった。彼女はコンゴのジャングルの中に生息していたのだが、何かの作用によって私と同じようにこの東京都郊外の街に連れて来られたのだ。その目は私が実はワニであることを完全に見抜いていた。そしてこう言っていた。私も同じ境遇なのだと。彼女のコンゴもまた、完全に失われていたのだ。彼女はそのものすごく強い握力で私のスーツの裾を掴んでいた。そしてその手の感触を通して、何かを伝えようとしていた。それは力強く、前向きな何かだった。
私は手すりから身を離し(頬には錆びがこびりついていた)、彼女に手を差し伸べた。少女はスーツの裾を離し、その手を一度強く握った。これでもか、というくらい強く。その痛みは私の中の原始的な部分を刺激した。ダイレクトに。そしてそのままどこか奥深くへと潜っていった。彼女はやがて手を離し、学校へと去っていった。私はもはや何かに噛みつきたいとは思わず、ただそこにいて、下を流れる車の流れを見つめていた。そしてこう思っていた。こここそが私のアマゾンなのだ、と。私はここで生きていくしかないのだ、と。
ということで私は家に帰り、95パーセントを占めるワニの部分を意識の底深く沈め、一人の人間として生きていくことにした。もちろん完全に、ではない。私はいつまで経っても本当はワニのままだろうし、それを密かに誇りに思うことだろう。ただ外目にはまともな人間らしく振る舞う、ということだ。そしていつか失われた私のアマゾンを、何らかの方法で再現しようとするかもしれない。たとえば絵や、文章という形にして。文章? まあそれも悪くないかもしれない。私は文章を書くことが得意ではないが――そんなことができるワニは限られている――やってできないことはないだろう。世の中にはたくさんの不必要な文章が満ちている。そこに私の試みが一つ加えられたところで、今さら深刻な環境破壊にはなるまい。そしてそこにおいて私は真の自分自身となるのだ。誰がなんと言おうと。




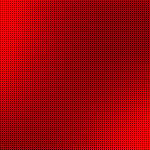
村山亮様
今回も読ませていただきました。
「ワニ」という作品はどこかカフカの「変身」を想起させます。
感想としてはもう少し作品にパワーが欲しいかななんて思いました。
関係ないですが翻訳された海外の本って原文で読むのとは印象が変わるのでしょうかね。
関係ないこと言ってすみませんが、度々感想失礼しました。
パワー不足は申し訳ないとしか言いようがないです。でもとにかくこの作品は、まったく別の以前書いたものを手直ししているときに、どうしても書きたくなって書いたものです。何の意気込みも、責任もありません。いつの間にかワニになっていたのです・・・。ただそれだけです。
翻訳の件は、作品によって違うとは思いますが、ときどき古い本を読むと、これを原文で読めたらきっと素晴らしいだろうな、と思うことがあります。特に流れの悪い翻訳を読むとそう思うかも。