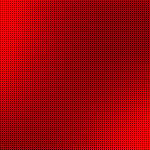私は風だ。いつから風だったのか、そしていつまで風のままでいるのか、私自身にも分からない。しかしとにかく私は風なのだし、カラスでもなければイボイノシシでもない。それは――少なくとも私には――幸運なことのように思える。そして今のところ私は、その境遇に満足している。
私は主に日本列島の上空を飛び回っている。誰が決めたのかは知らないが、それぞれの風にはそれぞれの担当地域が決まっている。ただそれもだいたいの範囲であって、そこまで厳密に区切られているわけではない。例えばこの前北海道のあたりを飛んでいたら、オホーツク海を越えて北風がやって来た。
「なあ、俺はあんまり冷えちまったよ」と身を震わせながら彼は言った。
そこで我々は身体の一部を交換することにした。風というのは実体があるようでないものだ。だから風と風との境目はとても流動的で、大方の場合好きなように身体の一部を交換することができる。
私は彼の身体の冷えた部分を受け取り、彼は私の身体の温かい部分を受け取った。
「じゃあな、ありがとうよ」と北風は言い、カムチャツカ半島目指して帰って行った。
下を見るとちょうど我々が出会った所に厚い雲ができていた。そろそろ雨か、雪が降り出すだろう。風と風が出会う所にはいつも雲ができる。
私は夏に都会を吹き抜けるのが好きだ。その時私は東京の上空を吹き渡っていた。通りを歩く人々はだらだらと汗をかいていて、私が通り抜けるとうれしそうな顔をした。私はそこでオフィスビルの自動ドアから飛び出してきた、ごく小さな風に出会った。
「ねえ、こんにちは」とその小さな風は言っていた。「私はエアコンの風なんです」と彼女は言った。「とても涼しいでしょ」
「ああ、確かに」と私は言った。
「でも私たちすぐに死んじゃうんです」
「人工的なものはどうしても長続きしないんだ」と私は言った。
「ときどきあなたみたいな自然の風がすごくうらやましくなるんです」と彼女は言った。「私も頑張ってあなたみたいな清々しさを出そうと思っているんですけど、どうしてもそれができなくて」
「この感じを出すには時間がかかるんだ」と私は言った。「それに空と一体になっている必要がある」
「空と一体になるってどんな感じなんです?」
「私が空になり、空が私になる」と私は言った。「空というのは限界を持たないものだ。それは宇宙につながり、宇宙はそのまた先の宇宙につながっている。空につながることによって私は限界を持たないものになる。そして我々は移動することによってそれを成し遂げるんだよ」
「なんだか難しそうですね」
「難しくなんかない」と私は言った。「結局のところ風というのはただの移動に過ぎないんだ。私が言いたいのはそれだけだよ。そして移動を続ける限り我々は自由でいることができる」
「ただの移動としての私が死んだら、そのあとはどうなるんでしょう」
「どうにもならない。移動が止むだけだ」
その夏私は太平洋に繰り出し、見渡す限りの海の上を吹き渡っていた。何の障害物もない海上を吹き抜けるのは私にとってこの上ない喜びである。私はそこでエルニーニョ現象に出会った。私を見ると彼はうれしそうにこちらに近づいてきた。
「やあ、久しぶりだね」と彼は言った。「こっちまで出て来るのはずいぶん久しぶりじゃないか」
「そうだな」と私は言った。「日本が私の持ち場だから」
「君は律儀な男だな。偏西風なんて一年中世界を飛び回ってるぜ」
「偏西風には偏西風の役割がある」
「まあそうだな」と彼は言った。「それにしても今年の夏は暑かっただろう。俺も相当頑張ったからな」
「どうしてそんなに頑張る必要がある?」と私は聞いた。
「太陽の奴が俺を炊きつけるからだよ。おい、こら、もっと世界を熱くしろってね。そう言われたら力の限り頑張るしかないじゃないか」
「暑さのせいで今年も沢山の人が死んだ」と私は言った。
「暑くても寒くても毎年沢山の人が死ぬんだよ」と彼は言った。「生まれては死んで行く。風みたいなものさ」
「ラニーニャ現象はどうしてる?」
「あいつは来年頑張るってさ」と彼は言った。「でもあいつって陰気だよな。もうちょっと人生を楽しめばいいのに」。そこで彼は南米大陸の方を向いた。「でもまあいいや。それがあいつの生き方だもんな。俺もちょうど休みたいと思っていたところだし、来年は彼に任せるよ」
日本列島に帰る途中、一頭の大きなクジラを見た。私はクジラと言葉を交わすことはできないが、彼(あるいは彼女)はなんとなく私の存在を認識しているようにも見えた。私は人間になりたいとは思わないが、クジラにならなってもいいと思う。あるいはそれは水中を泳ぐという行為が、風として地上を吹き渡る行為に似ているからかもしれない。それともただ単に大口を開けて、大量のプランクトンを丸飲みにしたいだけかもしれない。
夏が終わると、列島の南方から台風がやって来た。台風はいつも理不尽で、暴力的だ。それでも私は、何故か彼女を嫌いになることができない。
「ちょっとどけなさいよ」と石垣島のあたりで彼女は言った。
「お久しぶりです」と私は言った。
「ああ、あんただったの。一年ぶりくらいかしら」
「そうですね。ちょうど一年ぐらいです」
「その後元気にしてた?」
「まあほどほどに」
「あなたはほら、いつも穏やかだから。でも私が代わりに地上をひっかき回してきてあげる」
彼女はそこで眼下に広がる南西諸島を見降ろした。
「離れてたほうがいいわよ」と彼女は言った。「何もかもあっという間に飲み込んじゃうんだから」
私は忠告に従って空のずっと上の方に避難した。その間彼女は日本列島を縦断し、地上のありとあらゆるものをなぎ倒して行った。暴風雨を起こし、河川を氾濫させ、人々の生活を混乱させた。ようやくのことで彼女が八戸のあたりから日本海に抜けた時、私は尋ねた。
「どうしてこんなことをするんです?」
「私には選びようがないのよ」と彼女は言った。「私はね、これが悪いことだとは思っていない。良いことだとも思ってはいないけど。結局これが私という存在のあり方なのよ。それは前もって決められていることなの」
「誰に?」と私は尋ねた。
彼女はそれには答えなかった。そして言った。「また来年」
「さようなら」と私は言ったが、その時にはもう彼女は温帯低気圧に変わってしまっていた。
十一月の東北地方、うらぶれた海岸に一人の青年が座っていた。彼は手にノートを持ち、どうやらそこに詩を書きつけているようだった。彼の前方では美しい夕陽が雲の隙間から顔を見せていた。
彼は海上を吹き渡る風についての詩を書いていた。彼は、なんとなく哀しそうに見えた。どうやら彼は人間でいるのにうんざりしていて、いっそ風になってしまいたいと思っているようだった。
「風として生きるのもなかなか大変なんだよ」と私は言ってやりたかった。風として生きるには間断なく移動を続けなければならない。もし立ち止まってしまったら、風はもう風ではなくなってしまう。それにそもそも我々は生きているのだろうか?もし生きているとしたら、一体何のために生きているのだろうか。私には分からない。私に分かるのはただ、自分がこのように存在し、常に移動し続けているということだけだ。
それでも生身の身体を持ち――束の間とはいえ――この地上で生きていくというのもきっと大変なことなのだろう。そう思うとなんとなく、彼に対する共感のようなものが湧いてきた。私は彼のすぐ横を吹き抜け、彼が大事に抱えていたノートのページをぱらぱらとめくり上げた。彼ははっとして顔を上げ、さっきまで私がいた空間を見つめた。でもそこに私はいない。私はすでに次の場所に移動している。