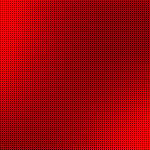その時僕は接続詞の森を通り抜けようとしていた。固有名詞の丘を登った先にある叔母の家を訪ねるためだ。叔母は最近健康がすぐれず、ベッドに寝たきりになっていた。僕は自分で焼いたバタークッキーを持って、彼女のお見舞いに行くことにした。
接続詞の森をただひたすら歩いていると、一匹のキツネに出会った。
「やあこんにちは」と僕は言った。
「そして、しかし、あるいは、もっとも」と彼は言った。
僕は首をかしげた。
「ああ、クッキーが欲しいということなのかな」と僕は聞いた。
「だから、もしくは、けれども、また」と彼は言った。
僕には彼の言いたいことが理解できなかった。まあそれも仕方ない。相手はキツネで、ここは接続詞の森なんだから。どうしたらいいか分からなかったので、僕はクッキーを一枚あげた。
彼はうれしそうにそれを受け取り、ぴょんぴょんとび跳ねながら去って行った。僕は先を急いだ。森には何が潜んでいるか分からない。次はキツネどころでは済まないかもしれない。
鬱蒼とした森の中を急いで進んでいると熊の姿が見えた。彼は抽象名詞の切り株に座っていた。僕は彼を驚かさないようそっと背後を通り抜けた。彼は頬づえをついて何かをつぶやいていた。
「正義、平和、愛、自由」
僕は音を立てないよう慎重に歩を進めた。
「苦悩、孤独、善、悪」
彼は考え事に夢中で、僕の存在に気付きもしなかった。
接続詞の森を通り抜けると、一転して開けた場所に出た。そばには形容詞の川が流れていた。川のほとりにはカワセミがいて、僕の頭上をせわしなく飛び回った。彼女はしきりに何かを訴えていた。
「さみしい、こわい、寒い、痛い」と彼女は言った。
「大丈夫ですか?」と僕は聞いた。
「おいしい、まずい、きれい、きたない」
「それはもしかしてクッキーが欲しいということなのかな」と僕は聞いた。
「すごい、楽しい、恋しい、優しい」と彼女は言った。
僕は鞄からクッキーを出し、細かく砕いて彼女にあげた。彼女はおいしそうにそれをついばむと、唐突に飛び上がり、ジグザグとした軌道を描いてどこかに去って行った。
形容詞の川を流れに沿って進むと、代名詞の橋がかかっていた。そこにはチンパンジーがいた。彼はせわしなく動き回って腕をぶらぶらさせたり、見えない何かに唇をまくりあげたりしていたが、やがて僕に近づいた。
「わたし、あなた、あなた、わたし」と彼は言った。
「もしかしてクッキーが欲しいんですか」と僕は聞いた。
「おれ、ぼく、きみ、それ」と彼は言った。
僕は鞄からクッキーを取りだした。すると彼は瞬時にそれをひったくった。
「あれ、これ、それ、そこ」と彼は言い、橋の手すりの上を器用にバランスを取りながら去って行った。
代名詞の橋の先には助詞の草原が広がっていた。助詞の草原にはリスがいた。
「てにをは、てにをは」と彼女は言い、僕の足元をちょこまかと走り回った。
僕は首をかしげた。
「と、へ、の、が」と彼女は言った。
僕にはこれまでの誰にも増して彼女の言っていることが理解できなかった。だからクッキーを差し出した。
「てにをは、てにをは」と彼女は言い、口いっぱいにクッキーをほおばって木の下の巣へと帰って行った。
助詞の草原の先には副詞の小道があった。狭い道を歩いているととぐろを巻いたニシキヘビが道を塞いでいた。彼は言った。
「とても、おそらく、きっと、あたかも」
彼はその太い腹をくねくねと這わせ、呪文のように副詞をつぶやきながらこちらに近づいた。僕は慌ててクッキーを差し出した。
「ようやく、ますます、さも、ちょっと」と彼は言い、クッキーを丸飲みにした。
そして「はるばる、漸次、暫時、順次」と言って藪の中に去って行った。
副詞の小道は固有名詞の丘へとつながっていた。僕は急勾配の坂をはあはあと息を切らせながら登った。すると丘を登りきった先に巨大なアメリカバイソンがいた。彼は低い声で唸るようにこう言った。
「アリゾナ、テキサス、アラスカ、ネバダ」
僕は試しにこう答えてみた。
「ユタ、ネブラスカ、カンザス、モンタナ」
彼はうれしそうに一声鳴いた。そこで僕は先を続けてみた。
「ニューヨーク、コネティカット、マサチューセッツ、ペンシルバニア」
今度は彼は怒ったように一声鳴いた。どうやら東部の州が嫌いらしい。
「ところでクッキーはいかがですか」と僕は聞いた。
「富士山、スターバックス、オーソン・ウェルズ、夏目漱石」と彼は言い、僕の鞄に頭を突っ込んで、残っていたクッキーを全部食べてしまった。僕の鞄は彼の唾液と鼻水でべとべとになってしまった。
「プリンス、マドンナ、マイケル・ジャクソン」と彼は言って、満足そうに去って行った。
僕は固有名詞の丘を登り切り、叔母の家に向かった。もうすぐ到着というところで、どこからか動詞の岩が転がり落ちて来た。人の背丈ほどもある丸い岩だ。その変な音に気付いたからよかったものの、危うくぺしゃんこに潰されてしまうところだった。それはこういう音だ。
「落ちる、転がる、食べる、戦う、迸る」。僕はそれを間一髪でよけた。
「生きる、死ぬ、滞る、跪く」。それは勢いを増してごろごろと転がって行った。幸いなことに、岩はクッキーを要求しなかった。
僕はようやく叔母の家に辿りついた。結局ここに来るまでにすべてのクッキーを使い果たしてしまったわけだが、叔母はそんなことは気にしなくていい、と言ってくれた。気持ちだけで十分だと。気持ちこそが大事なのだと。
開け放たれた窓からは、形容動詞の風が吹き込んできた。
「荒涼たり、切々たり、清らかなり、静かなり」
僕は深く息を吸い込んだ。
「明朗なり、堂々たり、洋々たり、寂寞たり」
そうだ。家に帰ったら詩を書いてみるのもいいかもしれない、と僕は思った。