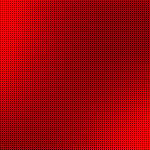昨日の夜部屋に幽霊が出た。
それは白い死装束のようなものを着た、髪の長い女の幽霊だった。どうして幽霊だと分かったかというと、身体が半分透けていたからだ。まるでクラゲみたいに。僕は仕事終わりに一通り筋トレをして(腕立てと腹筋)、シャワーを浴びて部屋に戻ってきたところだった。タオルで濡れた髪の毛を拭いて、ふと鏡を見ると、背後に何かがいた。何か、見慣れぬものだ。もちろんそれが例の幽霊だったわけだが、なぜか僕はそれほど驚かなかった。あるいは驚くほどの余力がもはや残っていなかったのかもしれない。
「どうもこんちは」と僕は言った。
幽霊は何も言わなかった。ただそこにじっとしているだけだ。
「こんちは」と僕はまた言った。「何か用ですかね?」
幽霊は相変わらず何も言わなかったが、なんだか気まずそうな空気は察することができた。あれ? こんなはずじゃなかったのにな、とその顔は言っていた。
「何か言ったらどうなんです?」と僕は怒った振りをして言った。「あなたは僕の貴重な時間を奪っている。そんなところでじっとして、一体何を求めているんですか?」
「えっと・・・あなたの命です」と彼女は言った。それは意外にも可愛らしい声だった。
「命?」と僕は言った。「そうか。あなたは僕の命が欲しいんだ。じゃあとっとと持って行ってください。特に惜しくもないから」
「え? 惜しくないんですか? でもそれって・・・」
「普通じゃない?」
幽霊は頷いた。「あなたおかしいですよ」
「いや、おかしくない」と僕は言った。「というかこっちが教えてほしいくらいなんです。一体どうして我々は生きなくちゃならないんですか? 地球温暖化が進み、外国人差別が横行し、Windows7のサポートは打ち切られ、世間では新型コロナウィルスが流行しています。メジャーリーグはなかなか始まらないし、僕は二十八にもなっていまだアルバイトをしている。リンゴとジャガイモの価格は軒並み上がっています。ねえ、一体どこに生きるだけの意味があるというんです?」
幽霊はちょっと困ったみたいだった。きっとそんなことを言われるとは予想もしていなかったのだろう。彼女は自信のなさそうな顔でこう言った。「ええと、でも、やはり物事の良い面を見れば・・・」
「たとえば?」
「たとえば、そうですね・・・。ええと・・・」
「ほら、言えないんだ。あなただって世の中に何一つ良いところが見つからなかったから、そんな幽霊になっちゃったんでしょう? そもそも一体何があったんです?」
「ええとですね、好きな人に振り向いてもらえなくて・・・」
「それで自殺したんですか?」
「いや、そうじゃなくて・・・階段で足を踏み外して」
「それで死んじゃったんだ」
「そうです。はい」
「それで、どうしてそんな格好しているんですか?」
「いや、ほら、幽霊といえばこんな感じじゃないですか? みんながイメージする」
「それはちょっと古いですよ」と僕は言った。「ねえ、時は2020年なんですよ。一体いつだと思っているんですか? 幽霊だってアップグレードしなければならない。そうだな、たとえばブロッコリーを持つとか」
「ブロッコリーを?」と彼女は言った。心底驚いたみたいだった。「ええと、一体なんでブロッコリーを?」
「そんなの僕に聞かないでくださいよ。まったく。僕が言いたいのは、そういう世間的なレッテルをひとまず引っ剥がすべきだ、ということなんです。そもそも何なんですか、そのボサボサの髪の毛は。一体この前シャンプーしたのいつなんですか?」
「二百年くらい前ですかね・・・はい」
「僕は思うんですがね、これからは幽霊も清潔にしなくちゃなりませんよ。時節も時節ですしね。はっきり言ってこれだけ現実の世界に脅威があると、人々は幽霊のことなんか考えている暇がないんです。僕は現実に生きている人間の心の方がずっと危険だと思いますね。そうは思いませんか?」
「まあ」
「結局あなた方はホラー映画にでも出て、はした金稼いでいればいいんだ。それで幸せなんでしょう? でも僕らには僕らの考えるべきことがある。と、いうことでお引き取り願えますかね」
「でもここが私の持ち場なんですよ。本来あなたは私に驚いて、絶叫するべきだったんです。そこで物語が終わる。めでたしめでたし」
「ええ? じゃあ叫べばいいんですか? こんな時間に。絶対に苦情が来ますよ。あの部屋の住人は薬物か何かをやっているってね。それで幻覚を見て叫び出したんだって」
「いや、そこをなんとか」
「なんとか、って、驚いてもいないのに叫ぶわけにはいかないでしょう? あなたにはプライドってものがないんですか?」
そのとき幽霊が心底驚いた顔をした。彼女は僕の背後を指差して言った。「ねえ、後ろ。後ろ・・・」
「え? 後ろ? その手には乗りませんよ。まったく。頭の構造が一万年くらい遅れているんだから。え? 後ろに何があるって・・・」
ギャー!!! と僕は叫んだ。叫ばざるを得なかったのだ。そこに何があったのかは・・・皆さまの想像にお任せします。少なくもブロッコリーではなかったけれど。
幽霊は納得したらしく、その後すぐにどこかに消えていった。僕は相変わらずアルバイトをしています。ああ、自由になりたいな、といつも思っています。でも幽霊になるというのもなかなか大変そうですね。話によれば何か問題が起きたとしても労災は利かないそうです。だってもう死んでいるじゃないか、というのが映画会社の言い分だそうです。時給はチョコレートひとかけだとか。まったく。生きるのも大変ですが――あるいはさほど大変でもないのだろうか?――死ぬのもそれはそれで大変です。彼女はその後シャンプーとリンスを買ったそうです。生前の貯金が役に立ったとか。皆さまも健康に気を付けてください。それでは。

最近贅沢をしたくなったときには、ブロッコリーを蒸して食べます。はい・・・。