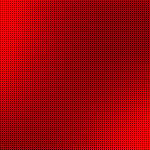「当時俺は深刻なテレビゲーム中毒に陥っていた」と彼は言った。
それはどんよりと曇った六月の末のことで、僕らは二人とも二十六歳だった。彼は仕事をしておらず、僕は今勤めている会社をあと二週間で退職しようとしていた。もっとも次に何をやるのかは、いまだに決まっていなかった。
「テレビゲーム中毒?」と僕は言った。それは少々意外なことだった。というのも彼は何かの中毒になるようなタイプには見えなかったからだ。いつも活動的で、何かに没頭している。旅行をするのが好きで、真っ黒に日焼けしている。酒はほどほどに飲むが、煙草はやらない。テレビゲーム中毒?
「それは・・・大学を卒業したあたりのことか?」と僕は言った。
「そうだ」と彼は言って頷いた。我々は僕の狭いアパートの部屋にいた。僕が椅子に座り、彼がベッドに座っていた。時刻は午後三時だった。日曜日の午後三時だ。一週間で最も憂鬱な時刻、と僕が信じている時間。
「君も知っての通り、俺は君が卒業した二年後になんとか卒業した。どうしてもうまくいかなかったら教官を買収しようとしていたんだが、まあその必要はなかったみたいだ。まったく。全然授業に出なかった割にはよくやった方だと思うよ」
「中退するという選択肢はなかったのか?」
「まあ自分では別にそれでもよかったんだが・・・。とりあえず卒業だけはしてくれ、というのが両親の希望だった。まあ、俺はほら、こんな性格ではあるんだが、俺の活動の資金源は彼らだからな。それくらいは叶えてやらなくちゃなるまい、と思ったんだ」
彼の実家は老舗の菓子店を経営していて、なかなか裕福だった。そしてその仕送りで、彼は好き勝手生きてきたのだ。僕とは全然状況が違う。
「まあそれで卒業はしたわけだ」と僕は言った。
「うん。まあ自分ではそんなことはクソどうでもいいと思っていたけれどね。とにかく学生という肩書が外れた今、俺は真の自由を手にしたのだ、と思った。なにしろ人生は短いからね。これで本当の意味で好き勝手生きられるぞ、と思ったんだ」
「しかし」
「しかし」と彼は言って首を振った。その目には哀しみの色が読み取れた。「なんだか想像していたのと違うんだ。学生の頃俺はもっと元気だった。元気で、生き生きとしていたんだ。いろんなところに旅行に行った。君と一晩中酒を飲んでいたこともあった。奇妙な人々と知り合いにもなった。いろんな変なことをした・・・。そしてこれこそが人生なのだと思っていた。くだらない試験勉強なんかに時間を費やして、結局は退屈なサラリーマンになるのなんてまっぴらだと思っていた」
僕はただ黙って続きを待っていた。
「でも一旦卒業してしまうと、俺は急に心細くなってしまった」と彼は先を続けた。「両親は頼めば金を出してくれた。いずれ店を継ぐから、という約束をしていたからだ。まあ俺としてはそんなつもりはまったくなかったわけだが、ほら、さっきも言ったように人生は短いじゃないか? だとしたら親の金だろうと何だろうと、使えるものは使っていくしかない」
「まあみんながみんなそんな状況に置かれているわけじゃないけどね」と僕は言った。
「それはきっとそうなんだろう」と彼は言った。「でも俺としてはそんなことに罪悪感を感じている暇もなかったんだ。なにしろ生きることに忙しかったからだ。やりたいことのリストが毎日頭の中で更新されていった。俺はそれを辿るだけで精一杯だったんだ」
「でも何かが今までとは変わってしまった」
「そう、その通りなんだ。大学にいる頃はそれでよかった。大人になんかなるものか、と思っていた。だってみんな目が死んでるじゃないか? 日々生活のために金を稼いで、休みの日にはただぼおっとして時間を潰す。頭だって悪くなる。視野を広げようという努力をしないからだ。俺はそんな人間にはなりたくなかったんだ」
「僕だってなりたくないね」と僕は言った。
「まあそうだろう。それは当然のことだ」と彼は言って頷いた。でもそのすぐあとに溜息をついた。彼が溜息をつくのを見たのは、これが初めてのことだった。「しかしだね、いざ大学を卒業してみると、俺はただのなんでもなしに過ぎなかったんだ。ただの無職の男だ。前は別にそれでも構わないと思っていた。システムに尻尾を振るくらいなら無職のままでいいじゃないかとね。しかし実際にそういう状況に置かれてみると、それがかなり孤独なことであることが分かった。何にも守られていない、というかね」
「そういえばあの頃から急に連絡が途絶えたんだよな」と僕は言った。その頃僕はさほど面白くもない会社の仕事を覚えるのに四苦八苦していた。もっとも覚えたところで、それはそれで自分が嫌になったものだったが。
「それは君に連絡するのが正しくないことであるような気がしたからだ」
「正しくない?」
「うん」と彼は言って頷いた。その顔は確信に満ちている。「というのも俺はあの状況を一人で乗り切らなければならなかったからだ。そのことが本能的に分かったんだよ。きっと君に連絡して話を聞いてもらえれば精神的に楽になるだろう、ということは分かっていた。今までみたいに周囲の愚痴を言ってな。でもそれじゃあ駄目なんだ、という感覚があった。どうしてかそう思ったんだ。自分はここを一人で乗り切らなきゃならんぞ、と」
「それは自分の成長のために、ということかな?」と僕は言った。
「まあ要するにそういうことだったんだろう。自分が未熟であることは知っているつもりだったが、いざその事実を突きつけられてみると、これはこれでなかなかきついものだ。でもきついということは、すなわちちゃんと身体に効くということだ。一種の筋トレみたいに」
「まあ一つの考えではあるな」
「一つの考えというか事実だ」と彼は言った。そしてまっすぐ僕の目を見た。「そういう観点からいえば、あれは俺にとってどうしても必要な時期だったんだろう。今ではそれが分かる」
「それで・・・その頃からテレビゲーム中毒になった、ってわけか?」
「まあそういうことだ。以前にはゲームなんてほとんどやらなかったのにな。孤独に、部屋の中にこもっていると、何かをやりたくて仕方がなくなってくるんだ。でもその何かが分からない。今までだったら釣りに行ったり、山登りに行ったり、ただ単に街を探検したり、そういうことで満足できたんだ。俺は極めてシンプルな人間だったんだよ。ご存じの通り」
「しかし」と僕は言った。
「そう、しかし、その頃から何かが変わってしまったんだ。俺はもう以前のような野生児ではないのかもしれない、とだんだん思い始めてきた。この俺がだぜ? 頭の中はやりたいことリストで満ち満ちていたのに、今ではそのどれもがくだらないことのように思えた。なんというのかな、同じところを行ったり来たりしているだけじゃないか、という感じがしたんだ。なあ、君はそういう感覚を抱いたことはあるか?」
「実をいえば毎日そう感じている」と僕は正直に言った。「君も会社で働けば分かるよ。毎日同じことの繰り返しだ。もちろんちょっとした変化はある。長く働けば給料も上がる。でもそれだけなんだ。それはどこにも行かない行為なんだ。限られたフィールドで完結してしまう。もちろんだからこそ金を稼げるわけだが」
「ふうん」と彼は言った。もっともさほど真剣にはこちらの話を聞いていないようにも見えたが。「まあいずれにせよ、俺はそんな感じで生きていたんだ。それでだんだん外にも出なくなり、最初にパソコンで簡単なゲームをやり始めた。あの四角いマスの中に爆弾が仕掛けられているやつだ」
「マインスイーパー」と僕は言った。
「そう、それだ。マインスイーパー。始めはルールも分からなかったが、やっているうちにはまってしまった。俺は寝食も忘れてそれをやり続けた。一週間くらいそれをやっていたかな・・・。で、そのあとは、そのほかのゲーム。トランプの一人遊びのやつとか、あとはコンピューターとチェスで対戦したりとか・・・。とにかくひたすらやった。時間がどんどん消えていくのが分かった。それは文字通り消えていくんだ。まるでバケツで掬って、その辺に撒いてしまうみたいに。本当はそんな風に時間を使うべきでない、ということは自分でもよく分かっていた。俺はこんな画面から離れて、本当の現実と向き合わなくちゃならないのだ、と。でもそれができないんだ。腰を上げることができないんだ。それがゲーム中毒の怖さだ。一旦入り込んでしまうと、なかなか抜け出すことができない。恐怖が頭の中を支配する。そんなことならいっそ、一生こうして時間を潰していたらいいじゃないか、と思うようになる」
「当時は全然外に出なかった?」
「まあ数日に一回出るかどうか、だ。近所のコンビニに食料品をまとめて買いにいく。はっきりいって食いものなんてなんでもよかったから手当たり次第目についたものをカゴに放り込んでいった。それでクレジットカードで払うんだ。あの頃は髪も切ってなかったし、髭も剃っていなかったから、きっと俺は山小屋で隠遁している仙人みたいに見えたんじゃないかな」
「ゲーム仙人」
「そう、ゲーム仙人だ」と彼は言った。「それで、パソコンの中のゲームを一通りやり終えてしまうと、今度はネットで最新型のゲーム機を買うことにした。そんで手当たり次第面白そうなソフトをダウンロードした。あとはもう、ひたすらやり込んでいたね。RPGから、スポーツゲームから、シューティングみたいなやつまで。やっていくにつれて、俺は結構こういう作業に向いているのかもしれない、と思うようになった。ひたすら一つのことに意識を集中する、というのかな。問題はそれがどんな意味においてもくだらない、と最初から知っていたということだな」
「その生活をどれくらい続けたんだ?」
「まあ、ざっと一年半くらいかな」と彼は言って眉をしかめた。あるいは当時の記憶は曖昧になっているのかもしれない。なにしろひたすらゲームをやり続けていたのだから。「うん・・・まあそれくらいだと思う。いずれにせよひどい時期だった。もう一度あれを繰り返すくらいなら死んだ方がましだと思えるくらい。でも俺には分かっているんだが、もし同じ状況に置かれたとしたら、俺はきっとまったく同じことを繰り返すだろうね。それは確実なことだ」
「僕にはそこまで深くテレビゲームにはまった経験がないから分からないんだが・・・」と僕は言った。「それでも君みたいな人間がなかなか出てこれなかった、というのは少々意外だな。だって君は現実生活の楽しさを十分理解していたじゃないか? もちろんゲームにだってある程度の面白さはあるだろう。でもつまるところ、それはやはり暇つぶしの手段でしかない。時間を右から左に移動する。しかしその間君はどこにも進むことができない。なぜならすべてはあらかじめプログラムされているからだ。それ以上のことは絶対に起きっこないんだ」
「君が言っていることはよく分かるよ」と彼はしばしの沈黙の後に言った。「しかし分かっているにもかかわらず、そこから出ることができないんだ。どうしてだろうな? うん。たぶんある意味では、当時の俺がそれを求めていたからなんじゃないかな。つまり狭い世界に入り込むことを」
「君が?」
「そう、俺が。まあ要するに俺にだって生身の人間らしきところは残っていた、ということなんだろう。俺は恐怖を感じていたんだ。世界の本当の姿を見ることに。そしてそこで生じる責任を負うことに。俺の言っている意味は分かるか?」
なんとなくは分かる、と僕は言った。
「そう、君なら分かると思っていた。結局俺は俺自身にならなければならなかったんだ。それが責任ということの意味だ。たとえば会社で働いて、金を稼いで、税金を納めて、家族を養ったところで、責任が果たされるわけではない。なぜならそれはこの世のレベルのものではないからだ」
僕はただ頷いた。
「まあいいさ」と彼は言った。「こんなこと、口で言ったって何の意味もない。君もご存じの通り」
「まあそれはそれとして、君は当時苦しんでいた」
「そうだ」と彼は言った。そして一度天井を見た。「俺は苦しんでいた。それは確かだ。当時は自分でもそれを認めようとはしていなかったがね。そう、一度両親が心配して様子を見に来たことがある。そんなこと今まで一度もなかったのにな。でも俺は居留守を決め込んでドアを開けなかった。まったく。たいした息子だよな」
「君らしくもないな。そんなことを言うなんて」と僕は言った。
彼は首を振った。そして言った。「なんというのかな・・・おそらく当時の俺は自信を失っていたのだと思う。自信だけが俺の唯一の取り柄だったっていうのにな。大学を出るまでは、俺はいろんなことに確信を持つことができたんだ。自分は何かに守られているのだと思っていた。何か尋常ではないパワーのようなものに、だ。そしてそれを感じている限り、決して悪いことにはならないのだ、と」
「でももうその確信が持てなくなっていた」
「そう。それはいつの間にか消えてしまったんだ。自分でも気付かぬうちに。そうすると俺はどうなる? 自信満々だった俺は、今ではただのひきこもりだ。ひきこもりのゲーム中毒だ。不思議なことに、世間から隠れれば隠れるほど彼らが敵対的なものに思えてきた。今まではなんとも思わなかったのにな。所詮自分の頭を使えない連中だ、くらいにしか思っていなかった。それがいざ部屋でゲームを続ける生活に入ってみると、どうしてか悪口を言われているような気分になるんだ。きっと俺の誇大妄想に過ぎなかったんだろうけどな。あいつは親の金で生き延びていて、ゲームばかりやっている、と。人間のクズだ、と」
「誰かに実際にそう言われたわけじゃないんだろう?」
「そうだ。実際には誰一人そんなことは言わなかった。でも駄目なんだ。あの頃は頭がどうかしていた。俺は世間から孤立した、一人のひきこもりになっていた。全世界が俺と敵対しているように、当時の俺は感じていた」
「そしてさらにゲームの中に逃げ込む、と」
「そうだ」と彼は言って深く頷いた。「延々とそのサイクルが続くんだ。一つのゲームをとことんやり切ると、間を置かず次に進む。というのもそうでもしないことには、呼吸すらうまくできなかったからだよ。俺はそれくらい重度のゲーム中毒になっていたんだ。手にたこもできた。視力はおそらく急激に悪くなった。でもそんなこともどうでもよかった。まるで砂漠で遭難した人が水を求めるみたいに、俺はゲームを求めていたんだ。おそらくポイントは、成果が数値として明確に示される、というところにあったんじゃないかと思う。時間さえかければテクニックは上がる。そうするとスコアも伸びていく・・・。その繰り返しだ。一より二の方が高い。二より三の方が高い。それは言うまでもないことだ。だとしたら、俺は精一杯努力しなければならない。その狭い世界の内部において」
「おそらく死が存在しないということが問題なんじゃないか?」と僕は言った。なんとなく話を聞いていてそう思ったのだ。
「そう、その通りだ」と彼は言った。そしてまっすぐ僕の目を見た。「君なら分かると思っていた」
「まあ、というか、ふとそう思っただけだよ。君はおそらく、否応なく存在する君自身の死から目を逸らしていたんじゃないか、と」
「俺自身の死はどこに存在するんだろう」と彼は言った。
「いや、僕にもよくは分からない」と僕は言った。「でもそうだな。強いていえばそれは単なる概念のようなものだ。だって僕ら二人はまだこうしてちゃんと生きているわけだから。でもいずれ死がやってくるという事実を抜きにしては、本当の生を語ることはできない。なんとなくそう思うんだよ。だってもし明日死ぬんだとしたら、そんなくだらないゲームのスコアなんてどうでもよくなっちゃうだろう? 違うか?」
「違わない」と彼は幾分小さくなった声で言った。「全然違わない。君の言う通りだ。君は完全に理に適っている。しかし、にもかかわらず、というかだからこそ、俺はその恐怖を乗り越えることができなかったんだ。一年半もの間。もしこのまま死ぬんならそれでもいいじゃないかとすら思った。それくらいひどい状況だったんだ」
「でもなんとか抜け出した」と僕は言った。
「まあな」と彼は言った。そしてそのあとしばらくの間何かを考え込んでいた。その頭の奥で当時の記憶が渦巻いているのを感じ取ることができた。前進があり、後退があった。また前進があり、後退があった。そしてある日、決定的な瞬間が訪れる・・・。
「一体どうやって・・・?」と僕は訊いた。
「どうやったわけでもないさ」と彼は言った。その目は不思議な色の光を湛えていた。透明に近いが、本当は透明ではない。よく見ると何かが小さく揺れ動いているのが分かる。そんな光だ。「本当にどうやったわけでもない。というのも契機となったのは、ゲームをやめようとする努力を放棄することだったからだ」
「ええと、それはつまり・・・」
「つまりこうなったからにはとことん行けるところまで行ってしまおうと思ったんだ。俺はそれまで何度かゲームをやめようと試みたことがあった。でも駄目だった。一日ともたないんだ。変な汗が流れてきて、心臓がドキドキして、息切れがする。手がコントローラーを求めて震えている。そんな感じだ。耳はどんなゲームにもおなじみの例の魂のない音楽を求めている。その再現のない堂々巡りを、心から求めていたんだ。なぜなら俺にはしがみつくべきものが必要だったからだよ。そういう観点からいうと、俺はやはり生まれつき生命力が強いのかもしれないな。なにしろ生きている意味がないというのに、生きたいと欲していたのだから」
「生きる意味がない人間ほど生きること自体にしがみつくんじゃないかな」と僕は言った。
「まあそうだ。君はよく分かっている。でもそれがいざ自分のこととなると、そう冷静にも分析していられなくなる。なにしろ俺は自分がクズだと分かっていながら、そのサイクルから抜け出せなかったんだからな。まあとにかく、そうやってぐずぐずと生き延びていたんだが、あるときこう決意したんだ。もう行けるところまで行ってしまおうと。自分でも嫌になるくらいゲーム中毒を極めようとな。それで俺はほとんど睡眠さえ取らずにゲームをやり続ける生活に入ったんだ。食事の回数も減らした。外に出る頻度も、極限まで減らした。カーテンを閉めて、日光を遮った。というのも時間の感覚を麻痺させたかったからだよ。俺は自分を無理矢理狭い世界の中に閉じ込めたんだ」
「意識的に自分を外の世界から隔離したわけだ」
「まあそうだ。外に出たい、という気持ちが湧いてきたときには、無理矢理自分にこう言い聞かせた。なあおい、外の世界に何がある? と。全部くだらないものだ。くだらない人間がくだらないことをして時間を潰している。それも一生だ。奴らは自由を売って生きている。お前はその仲間になりたいのか? と」
「でも本当はそう信じていなかったんだろう?」と僕は言った。
「どうかな・・・。本当のところはよく分からない。でもとにかくそのときには、自分にそう言い聞かせる必要があったんだ。これは本能的なものだ。俺は自分を――自分の精神を――意識的に狭い小箱のようなものに押し込めていた。おそらくそこから自然に脱出したくなる機会を窺っていたんだと思う。そう。そのときの俺に必要だったのは、そういう自然さだったんだ。頭で考えた解決法じゃなくね。それが本当の必然性を持っていたときにだけ、自分は救われることができるだろう、と俺は思っていた。そしてその思いは今でも変わらない」
「それで、その試みはうまくいったのか?」
「結局二週間ほどその生活が続いた」と彼は言った。「要するに今までよりもペースを上げてゲームをやり続けたんだ。時間はこれまでにも増してどこかに吸い込まれていった。自分の魂と肉体が朽ち果てていくのが分かった。栄養も取らず、休養も取らない。ただひたすらレベル上げをやったり、ただひたすらサッカー選手を育てたりする。その繰り返しだ。音楽が――あのくだらない音楽が――頭にこびりついて離れなくなってしまった。生命を欠いた音楽。俺はどんどん機械のようなものに近くなっていく。心の動きがとことん強張っていくのが分かる・・・。
と、そのとき何かが切れたんだ。プツンとね。それまでかろうじて保たれていた集中力のようなものが、完全に途切れてしまっていた。俺は一種の達観した状態になって、画面を睨んでいた。カーテンを閉めているせいで、時刻が何時なのかは分からなかった。俺はしばらくその姿勢のままじっとしていた。何一つせず、何一つ考えなかった。ただそこにあった空間と時間とを、ひたすら睨み続けていただけだ。俺は自分が何かの瀬戸際にいるのだと感じていた。後ろにはこれまでの意味のない生活がある。そこに戻ることは簡単だ。なにしろゲームをし続けてさえいればいいんだから。あるいは就職して金を稼ぐか。要するに俺の中では、その二つは同じようなものとして位置していたんだ。動きを止めていること、というのがその二つの共通点だ。狭い世界に閉じこもって、発展を止める。延々と同じことの繰り返しだ。ただ少なくとも生き延びることはできる。
しかし前方にあるのはまた別の世界だった。それは俺にとっては未知の領域だった。俺はこれまで結構自分は自由に生きてきたのだと思っていた。君も知っての通り、まあ親の金を使って好き勝手やってきたからな。正直それが恵まれていると感じたことすらなかった。俺はとにかく今を生きなければならないのだ、と思っていた。
それが今回こんな風にゲーム中毒になっちまって、何かがうまくいかなくなって、それであらためて前方を見てみると、そこには見たこともない光景が広がっていたんだ。もちろん実際には自分の狭いマンションの一室にいるに過ぎない。カーテンはいまだ閉めきっている。だからそれはもっと精神的な意味合いでのことだ。まあ君には言っている意味は分かると思うが」
「まあ」ととりあえず僕は言った。「多少はね」
「多少分かれば十分だ。とにかく俺はそのとき一種の瀬戸際にいた。後ろに戻るのも、前に進むのも俺の意思次第だった。そして俺は自分の責任においてそれを選択しなければならなかったんだ。それはものすごく怖いことだった。こんな恐怖を味わったのは、生まれて初めてのことだ。俺はまるで、人生で初めて親とはぐれてしまった子どものように怯えていた。手がぶるぶると震えるのが分かった。周囲を見回して、何かヒントがないか探してみた。でもそんなものはどこにもないんだ。そして俺は本能的にはそれを知っていたんだ。というかずっと前から知っていたんだ。俺はこの先に進まなければならないのだ、と。ヒントもなければ道標もない。そういった空白のような世界に、自分一人の責任で進んでいかなくてはならないのだ、と」
彼はそこで一旦黙り込んだ。部屋は非現実的なまでに静かだった。まるで壁紙がすべての音声を吸い取ってしまったかのように。彼はやがて再び口を開いた。
「それで、俺はその宙ぶらりんの状態でしばらくじっとしていた。というかほかにしようがなかったんだ。俺は自分に自信を持とうと思う。でもその勇気がどうしても出せない。しかしだからといってかつていた場所に戻ることはできない。というのも、もう俺はその生活にうんざりしていたからだよ。ゲームをするのももう飽きた。指だって痛くなった。目もチカチカしている。耳は、これ以上くだらない音楽を聞きたくないと言っている。俺はどうすればいいんだろう、と俺は思っている。俺は一体どうすれば救われるんだろう、とな」
「でもきっと進むしか道はなかったんだろう」と僕は言った。
「まあな」と彼は言った。「要するに、それが俺という人間の一種の義務だったわけだ。なぜかは知らんが、そういう運命のもとに生まれたんだな、きっと。でもだからといって、そう簡単に勇気を出せるわけじゃない。俺はなんにもない空間から、それを引っ張り出してこなくちゃならなかったんだ。君には想像できるか? 君にはそこまで自分を信じることができるか?」
僕は首を振った。「たぶんできないだろう。おそらくはその直前まで行くこともできないんじゃないか?」
彼はそれについては何も言わなかった。ただ黙ったまま、目の前の空間を睨んでいる。相変わらず音はない。まるで海の底みたいに。
「まあ、とにかく俺はそういう状況に置かれていたんだ」と彼は話を再開した。「好むと好まざるとにかかわらず、ね。それでずいぶん長い時間そうやってぼおっとしていた。いや、意識を集中していた。まあどちらでも構わないか。俺は長い間重心を定めることができずにいた。まるで踏み出した足を、どこに着地させればいいのか迷っている人みたいに。と、そのとき台所で変な物音が聞こえたんだ」
「変な物音?」と僕は訊いた。
「そうだ」と彼は言って頷いた。「パン、という何かが破裂するような音だ。そしてそのあとに続いて、皿が割れる音が聞こえた。それも一枚じゃない。二枚とか、三枚とかだ。始めは地震がきたのかと思った。そのせいで皿が落っこちたのだと。でもそんなことじゃなかった。やって来たのは、もっと別のものだったんだ」
僕は何も言わず、ただ固唾を呑んで話の続きを待っていた。もっと別のもの?
「その物音は、時間が経つにつれどんどんひどくなっていった。ドン、という大きな音も聞こえた。どうやら壁に穴が空いたらしかった。なんとなく雰囲気でそれが分かった。俺は本当は立ち上がって様子を見に行くべきだったんだが、どうしても腰が動かなかった。というのもそこで何が起こっているのか、知りたくなかったからだよ。俺はできれば真実を見ることなく、平和に生きていたかった。でもそれが不可能であることを本能的に知っていた。なぜなら今向こうからそれがやって来ていたからだよ。
俺は固唾を呑んで何かがやってくるのを待っていた。それは台所を荒らしまくったあと、そっと俺がいた部屋に入り込んでいた。姿こそ見えなかったものの。俺にはその気配を感じ取ることができた。背筋に寒気が走るのが分かった。俺は全身から汗をかいていた。目をつぶろうとしたが、それも不可能だった。俺の意識はこれまでにないくらい鋭敏になっていた。空気のちょっとした動きが、手に取るように感じ取れた。俺は自分が死に近づいていることを本能的に理解した。
やがてその何かが俺に手を触れた。そういう感覚があった。それは実は形を持たないものだったのだが、俺には今その存在を感じ取ることができた。電気が消え、テレビの画面も消えた。ゲーム機も死に絶えた。すると本当の無音がやってきた。暗闇と無音。俺はそれに包まれながら、ただ俺自身だった。やがてその何かが俺の中に入り込んできた。そういう感覚があった。俺は息を止め、ただじっと耐えていた。心臓が一拍鼓動を飛ばしたのが分かった。脳が酸素を求めて喘いでいた。俺は頭の中で火のことを考えていた。燃え盛る火のことを。
ずいぶん時間が経ったあと、俺は自分が移動していることを知った。どうしてかは分からないが、その何かが後押しをしてくれたらしかった。俺は立ち上がり、一度大きく深呼吸をした。そして思った。さあ、これから生きなくちゃな、と」