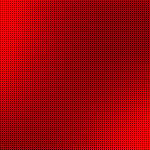頭が締め付けられるように痛い。ここ最近痛みが激しくなっているような気がする。私はその場で目をつぶり、ただじっとして頭痛が去っていくのを待った。頭の奥の方で変な音が繰り返し鳴っている。それは女の叫び声のようにも聞こえるが、間違いなくそうだと言い切れるほどの自信はない。それは、場合によっては風の音に聞こえなくもなかった。荒野を吹きすさぶ寒風の音。まあいずれにせよ、それほど心地良い音というわけではない。
その音は私の頭の中で執拗に鳴り続けていた。それは高くなったり低くなったり、奇妙なやり方で波を打ち、意識の奥で渦を巻いた。その音を聞いていると、まるで自分がアクロバティックなダンスを踊っているかのような気分になった。意識が高く跳躍し、空中で一回転した。上が下になり、下が上になった。右が左になり、左が右になった。気付くと腕の場所に脚がついていて、脚の場所に腕がついていた。首が奇妙な角度に折れ曲がり、見えるはずのない景色が見えた。そのようにして私はひどく混乱し、平衡感覚はどこか遠くに消え去った。重力が本来とは逆の向きにはたらいていた。
私はしばらくの間じっとして、重力が本来の向きに戻るのを待った。あのかん高い音は(やはり女の叫び声のように聞こえる)少し小さくはなったものの、まだ執拗に鳴り続けていた。これは何なんだ、と私は思った。これは一体何なんだ?
ずいぶん経った後、私はためしに目を開けた。目を開けてみると世界はぐらぐらと激しく揺れていた。地震かもしれない、と一瞬私は思った。でもそれは地震のせいではなかった。街行く人々は平然とした顔ですたすたと私の横を通り過ぎて行ったからだ。揺れているのはどうやら私自身のようだった。
私は病院に向かった。こんな状態で仕事に行ったところで何もできまい。そのクリニックはオフィス街の中心にあった。もう十年もここに通い続けている。
医師によれば私には生まれつき脳に欠陥があるということだった。私は生まれつきある種の感覚が異常に敏感なので、定期的に脳をチェックし、破損した部分があればその都度治療を行わなければならない、ということだった。それが具体的にどのような欠陥なのかは結局誰も教えてはくれなかった。もちろん医師にも尋ねたのだが、彼の説明はなんだか歯切れが悪く、私にはまるで何かを隠しているように思えた。
まあいずれにせよ、私にとって重要なのは現実にそこにある痛みを取り除いてもらうことだ。痛みさえ引けばあとのことはもうどうでもいい。細かい理屈がどうであれ、本当の病名が何であれ、私にはさほど関係のないことだ。重要なのはこの身体を使って今をきちんと生きることではないか。それにこの治療には全額保険が効いたから、実際の病名が何であれ特に興味はなかった。
そこで行われる治療というのは、MRIのような器具の中に寝転んで、ただじっとしているというものだった。頭に専用のヘルメットをかぶり、暗くて狭い器具の中で一時間ほどじっとしている。だいたい器具に入ってすぐに麻酔薬を打たれる。中にいる間の記憶はほとんどない。だからまあ、こちらとしては楽なものだ。頭に痛みを感じたら器具に入る。目を覚ますとすべては元通りになっている。確かに意識を失っている間に何をされているか分からない、というのは不気味なものだが、これだけ医療が進歩した時代なのだ。基本的には彼らを信用してもいいだろう。
それでもその日の痛みはこれまで経験したことがないほど強いものだった。私はビル(ここの十八階にクリニックが入っている)のエレベーターに乗っている間もずっと目をつぶっていた。いつになく照明がまぶしく、攻撃的であるように感じられたのだ。私は痛みを紛らわすために、何か別のことを考えようとした。例えば今年度の国の社会保障予算なんかのことを。でも頭の中ではまだあの奇妙な音が鳴り続けていて、予算のことなんかあっという間にどこかに吹き飛んでしまった。
受付を済ませると、すぐに治療室に案内された。白衣を着た看護婦は心配そうに私を見つめていた。彼女は私が器具に入ると、いつものように手際よく麻酔薬を注射した。ちくりという痛みが走ったかと思うと、次の瞬間にはもうあっという間に眠りに落ちていた。
目を覚ましたのは二時間後だった。いつもの倍の時間がかかっている。私は器具から出ると、様子を見に来ていた医者に尋ねた。
「一体なぜ二時間もかかったんです?」
「症状がずいぶん悪化しています」と彼は言った。「こんなことはあまりないことなんですが」
「そんなに悪いんですか」
「まあでも、治療を続けていれば大丈夫です。だってもう痛みは引いたんでしょう」
「ええ、もうすっかり引きました」
「それなら大丈夫です。お仕事頑張ってください」と彼は言った。
「それはもう」と私は言った。
私は政府直属の機関で働いている。医療保険に携わる役所で、煩雑な事務を次から次へと片付けていく。確かに面白い仕事とは言えないが、それなりにやりがいを感じながら日々仕事をしている。毎日やるべき仕事があり、健康で、給料ももらえる。それ以外に一体何を望めばいいのか。
仕事をしているとときどき意識が宙を飛ぶような感覚がある。意識が空を飛んでいる間、残った私の肉体は純粋な機械として定められた指示に従う。ときどき油を差す必要はあるが、休息の必要はない。まあ有能な機械だと言ってもいいと思う。仕事が終わると私の意識は肉体に戻り、全身に残った心地よい疲労を味わう。そして、論理的であるというのはなんと素晴らしいことなんだろう、と思う。すべての現象は意図的に把握され、決して「迷う」ということがない。直線と数式による世界だ。そこに淀みや綻びが入り込む余地はない。そんなものは全く非論理的だからだ。
結局その日は病院に行って遅れた二時間分残業をし、家に帰った。誰もいないオフィスで黙々と働くというのもたまには悪くない。聞けば昔は日本人の大半が残業をしていたらしい。そんなことは今では考えられない。
家には妻と二人の子どもがいる。上の子が女で、下の子が男だ。二人ともまだ小さい。とても元気で、いたって健康である。全く申し分ない。妻は私より二つ年下で、まあ美人だと言ってもいいと思う。あるいは私の贔屓目なのかもしれないが、それでもほかの人よりは美人だと思う。彼女は気立てがよく、穏やかで、料理が上手い。全く申し分ない。
私はいつもより二時間遅く帰宅したわけだが、彼女はまだ夕食を食べずに待ってくれていた。
「なんだ、先に食べてくれていてよかったのに」と私は言った。
「あなたと話をしながら食べたかったから」と彼女は言った。
私達は一緒に彼女の作ったハンバーグを食べ、赤ワインを飲んだ。ポテトサラダと茹でたブロッコリーもあった。相変わらず美味い食事だ。「ねえ、知ってるかい?」と私はふと思い出して言った。「今日古い医療保険の資料を見ていて知ったんだが、それによれば昔は『アルコール中毒』なんてものがあったらしい」
「アルコール中毒?」と彼女は不思議そうに聞き返した。
「そう、アルコール中毒。朝から晩まで酒を飲んで、それでも酒を飲むのをやめられないんだ。かつてはそういう病気があったんだよ」
「分からないわ」と彼女は言った。「もし本人が飲みたいのなら好きなだけ飲めばいいじゃない。それで、飲みたくなくなったらやめればいいだけの話じゃない」
「その通りだ」と私は言った。「でもやめたくてもやめられなかったんだって」
「私には分からないな」と彼女は言った。
「うん。君は健康だからね」と私は言った。「でも昔はアルコールだけじゃなく、ほかにもいろんな中毒があって、そのせいで国の医療保険制度は破綻の危機に瀕していたということだ。非科学的な時代に生まれた人々は不幸だと言うべきだね」
「ほかにはどんな中毒があったの?」
「例えば食べ物。世の中にはすごい数の肥満の人がいたらしい。そんなの考えられるか?適切な食べ物を適切な量食べればいいだけじゃないか。昔の人はなんでそんなことも考えつかなかったんだろう」
「時代が時代だったから」と彼女は言った。
「まあね。我々は今の時代に生まれて幸運だったと言うべきだよ。人々は健康になり、医療費はほとんどかからなくなった。寿命も延びたが、老人たちは施設で適切に管理されていて、社会の迷惑にはならない」
「でもあなたはどうなの?」と彼女は言った。「今日だって病院に行って来たんでしょう」
「そうだな。僕の欠陥は生まれつきのものだからね。こればかりはどうにもならない。でもその分一生懸命働いているし、国には十分お返しをしているつもりだよ」
「医療費のことなんてどうでもいいのよ」と彼女は言った。「頭の痛みは大丈夫なの?」
「そうだな、確かに痛みは増しているような気がする」と私は言った。「今日の治療もいつもの倍の時間かかった。でも大丈夫だよ。今はもうすっかり痛みは引いた。明日もちゃんと働ける」
「それならいいけど・・・」と彼女は言った。
私は適切な量の食事を摂り終わると、適切なやり方で歯を磨き、適切な温度の風呂に入った。そしてきっちり二十分間身体をほぐすためのストレッチをして、それからベッドに入った。私は普段は夢を見ない。毎晩同じ時間に眠り、毎朝同じ時間に起きる。それこそが健康な生活というものだ。でもきっとあの頭痛が関係しているのだろう。その夜私は奇妙な夢を見て目を覚ました。それはこういう夢だ。
私は自転車に乗ってアスファルトで出来たレース用のサーキットをぐるぐると走り続けている。まわりには同じように自転車に乗った人々が大勢いて、同じようにぐるぐるとそのサーキットを走り続けている。彼らは一心不乱にただぐるぐるを繰り返しているのだが、私はどうしてもサーキットの外に出たいと思っている。なぜそんなことを思っているのかは分からない。私は隙を見てはコースの外側をちらちらと眺めている。私には好奇心がある。そこには一体何があるのだろう?でもあまりに多くの人がまわりにいるため、なかなか外側を眺めることができない。それでも私は走りながら少しずつサーキットの外縁に近づいて行く。ようやくのことで一番端に辿り着き、外側を眺める。するとサーキットの外側は全くの暗闇だった。まるで宇宙空間みたいに。もしそこから飛び出してしまったら、まっさかさまに落ちて、二度と浮かび上がってはこられないだろう。私は冷や汗をかいて少しだけ内側に戻った。それでもそのサーキットの外側に出たいという思いは消えなかった。私はなんとか抜け道がないものかと目を凝らした。するとある部分にだけ細長い道が続いているのが見えた。最初は目の錯覚かと思ったのだが、それは確かに一本の道だった。ほかの人々はそんな道には一切目もくれない。あるいは彼らにはその道が見えないのかもしれない。でも私には確かに見えた。その道は暗闇の上をどこまでも遠くに伸びていた。私はタイミングを見計らいその道を進もうと試みた。それはとても細い道で、自転車で進んで行くのはとても危険に見えた。それでも私の決心は変わらなかった。私はどうしてもこのぐるぐるから抜け出したかったのだ。
しかしその細い道に入り込もうとする寸前になって、ひどい頭痛が私を襲った。それはこれまでに感じたことのないくらい強い痛みだった。私は堅く目をつぶった。よりによってどうしてこんなときに痛みがやって来るんだ。私はなんとかしてその痛みをやり過ごそうとした。しばらくすればきっと自然に引いていくはずだ。しかしその締め付けるような痛みは一向に去る気配を見せなかった。むしろそれはますます悪化していった。頭の奥の方で人の叫び声のような音が聞こえた。平衡感覚が急激に失われていった。私はバランスを崩して転倒し、自転車もろともアスファルトに激しく叩きつけられた。
幸運にもサーキットの外側には落ちなかったようだ。しかし私が転んだせいでまわりのライダー達も巻き添えを食い、次々に転んでいった。人々は後から後からやってきて、一人残らず転んでいった。私はぼんやりした目でその様子を眺めていた。転んだ人々は皆サーキットの内側に向けて吸い込まれていった。見るとサーキットの内側にもまた濃密な闇があった。それは渦を巻き、まわりにあるものを次々に呑みこんでいった。そして気付くと私もまたずるずるとその内側の闇に引きずり込まれていた。いやだ、まだ死にたくない、と私は思った。私はなんとかサーキットの外縁まで這って行き、そこに両手をかけて必死にしがみついた。しかし吸い込まれていく一群の人々が私の足を掴み、私を道ずれにしようとした。
「あんただけ逃げようってのか」と一人が言った。
「みんなが転んだのはあんたのせいなんだぞ」と別の一人が言った。
それでも私は足を掴んだ人々を蹴飛ばし、なんとか自分だけは生き残ろうとした。視線の先にはあの細長い道が見えていた。俺はなんとかしてあの道を進まなければならない。こいつらに道ずれにされるわけにはいかない。
しかしそのときまたしてもあの頭痛がやって来た。それはさっきよりもさらに勢いを増しているようだった。人間の叫び声のような音は今では耳をつんざくような轟音となって私の頭蓋に反響していた。私はもう気が狂ってしまいそうだった。私は縁にかけていた両手を離し、耳を塞いだ。もうこんな音は聞きたくない。頼むからあいつを黙らせてくれ。
しかし両手を離したせいで、当然のことながら私は内側の闇に向けて引きずり込まれた。そこでは煮詰めた墨汁のような闇が渦を巻き、まわりにあるすべてのものを吸い込んでいた。私は闇に吸い込まれながら、自分の医療費のことを気にしていた。転んだときにひどく身体を擦りむいてしまったのだ。それにほかの大勢の人々もまた怪我をしたはずだ。いくら全額国庫負担だからといって、国にこんな多額の医療費を負担させるのはさすがに気がとがめた。それもこれも、すべて私が転んだせいなのだ。でもふと気付くとまわりの人々はすでに一人残らず闇の渦に吸い込まれて消えてしまっていた。私は安堵のため息をついた。まあとにかく、と私は思った。消えてしまったのであればこれ以上医療費のことを気にする必要はない。しかしそんなことを考えているうちに私自身もまた闇の渦に呑み込まれ、この世界から消え去ろうとしていた。私の頭の中ではあの奇妙な音がまだ大音量で流れ続けていた。どうして誰もあの騒音を止めようとしないんだ、と私は思った。どうしてあんなものを野放しにしておくんだ。次の瞬間私は完全に闇の渦に呑み込まれ、視界がぷつりと途絶えた。そして空白が――完全な空白だ――世界を覆った。
私は全身に冷や汗をかいて目を覚ました。時計を見るとまだ眠ってから一時間しか経っていない。ベッドの隣では、妻が静かな寝息を立ててすやすやと眠りこんでいた。私は台所に行き、何杯も水を飲んだ。俺は一体どうなってしまったんだろう、と私は思った。俺の中で一体何が起こっているのだろう。
結局朝まで眠ることができなかった。こんなのは生れてはじめてのことだ。食事にも生活習慣にも気を配っている。それなのに一体なぜあんなひどい夢を見なければならないのか。
結局その夢のことは妻には話さなかった。余計な心配をかけたくなかったからだが――妻はかなり心配性なのだ――自分の身体の不調のことはできるだけ自分の中だけに留めておきたい、という思いもあった。
閉鎖回路 (2) に続く…