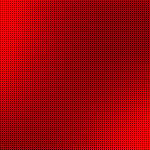「昨日俺はある重要な事実に気付いた」と彼は言った。
「重要な事実?」と僕は言った。
「そうだ」と彼は言って頷いた。「非常に重要な事実だ」
「それはつまり・・・どういうことなのかな?」
「それは、だ」と彼は言って、一瞬効果的に間を置いた。僕は思わず唾をゴクリと飲み込んだ。
「それは?」
「俺が俺自身だ、ということだ」。彼はそう言うと、もうそれ以上僕に用はない、とでもいうように、隣の自分の部屋に帰っていこうとした(ちなみにそのとき僕らは、僕の部屋の玄関先で話をしていた)。
「ちょっと待ってよ!」と僕は慌てて呼び止めた。「非常に重要な事実って、つまりそれだけ? 君が君自身だ、っていう・・・」
「はっきりいって、そんなことは前から気付いてはいたんだ」と彼は言った。「しかし昨日の夜、俺はそれを身を持って理解したんだ。腑に落ちた、といってもいいかもしれない。ということでだ、俺はそれを今から文章という形に移し替えようと思う。だからいつもみたいに邪魔しないでほしいんだ。たとえ寂しく思ったとしてもね。じゃあ」
僕は唖然として玄関に立ち尽くしていた。隣の部屋のドアがガチャンと閉まる音が聞こえた。いつもみたいに邪魔しないでほしい? と僕は思った。いつも夜中の二時とか三時に、こっちの都合なんかお構いなしに押しかけて来るのは彼の方じゃないか。
もっとも本心をいえば、彼が詩作に集中して僕のことを忘れてしまうのはたしかに少々寂しいことではあった。彼の突飛な思いつきは、僕にとっては一種のレクリエーションですらあったからだ。しかし我々ももう二十六なのだ。一人で時間を過ごすことをそろそろ覚えるべきだろう。
その日は日曜日で、仕事は休みだった。彼のように会社勤めをしていない人間には――彼は裕福な両親からの仕送りで生活していた――このような休日の貴重さはあまり理解できないだろう。それは朝七時半の出来事で、実のところさっきドアブザーが鳴って玄関を開けたときには、僕はまだ寝足りない状態だった。しかし彼との会話を経たあと、目が思いがけずぱっちりと開いていることに気付いた。もう一度ベッドに潜り込んだとしても、うまく眠ることはできないだろう。それに、と僕は思った。彼は彼の仕事をやっているのだ。僕は僕自身のことをやらなければならない。
といっても僕には彼のように「どうしてもやりたい」ということがなかった。それが一番の問題点だ。部屋で読書をしていてもいいし、あるいは映画を観に行ってもいい。しかしそのいずれにもあまり心を惹かれなかった。今は八月の始めで、外は非常に暑かったものの、僕はただ外を歩き回ることを選択した。
ハーフパンツにTシャツ、それにランニングキャップという格好で出たものの、日本の夏の暑さはここ最近明らかに尋常ではなくなっていた。ほとんど意地で一時間半ほど歩いてはいたが、さすがに頭がふらふらしてきたので、途中で喫茶店に寄って冷たいアイスティーを飲んだ。個人経営の小さな店だ。アイスティーそのものは美味いのか美味くないのか、それすらもよく分からないしろものだったが、少なくとも失った水分を補給することができて、僕の身体はとても喜んでいた。そのとき携帯電話を部屋に忘れてきたことに気付いたが、それはまあそれでいいや、と思った。かえって心が楽になるかもしれない。
店内には何組かの若いカップルがいたが、彼らを見ていて僕が連想するのは、死のことだった。一体どうしてそんなことを考えるのだろう、と僕は自分自身に問いかけた。あるいは僕は普通ではあり得ないくらいにひねくれた性格の持ち主なのかもしれない。それで幸せそうな人々を見ると、彼らが死んでいる様が頭に浮かぶのかもしれない。でもそれだけではなかろう、という思いもあった。真実とは死の脇に存在しているのだ、という考えがどこかにあったからだ。でも一体どこでそんな言葉を聞いたんだろう。真実とは死の脇に存在しているのだ。あるいは彼が――つまり僕の友人の彼が――そんなことを言ったのだろうか?
アイスティーがなくなって、氷がカラカラと音を立てるまで僕はそんなことを考えていた。お店のBGMはどこかで聞いたことのある曲だったのだが、どうしてもその曲名が思い出せなかった。古い時代に流行ったアメリカの曲だ、ということは分かっていたのだが・・・。そのメロディーは店を出てもなおしばらく頭の中を流れ続けていた。でも次第に暑さに紛れて、そのままどこかに消えてしまった。
川沿いの道を通って部屋に帰った。あの喫茶店で感じた死の気配はまだ僕の中に居残っていた。暗く、重たい。不吉な影を帯びている。僕は何か別のことを考えて――あるいはまったく何も考えないで――なんとかその気配を拭い去ろうとしたのだが、どのようにしてもそれは不可能だった。それはあるいはずっと前から僕の中に存在していたものだったのかもしれない、と思ったのは、ちょうど部屋に着いて玄関のドアを開けたときだった。
不思議なことに鍵は開いたままだった。あるいはうっかりして閉め忘れたのかもしれない、と思ったが、すぐにそうではないことが判明した。というのも部屋の奥から明らかに誰かが歩き回っている音が聞こえてきたからである。
警戒して覗き込んでみると、そこにいたのが彼であることが分かった。僕の隣人の、ついさっき「邪魔しないでくれ」と自ら言い放った彼だ。彼は今右腕にタオルをグルグル巻きにした状態で、せわしなくフローリングの床を歩き回っていた。そして僕の顔を見ると、安心したように「ようやく来たか」と言って、小走りでこちらにやって来た。
「どうして鍵を開けられたんだ?」と――当然のことながら――まず僕は訊ねた。
「鍵?」と彼は不思議そうに言った。「ああ、鍵のことか。そんなのはたいしたことじゃない。ずいぶん前にスペアの鍵を拝借しておいたんだ。ときどき喉が渇いたときなんかに、ビールを貰いにきたこともある。なんだ、君に言ってなかったか」
そんなこと聞いていない、と言おうとしたのだが、それよりもまず深い溜息の方が先に出た。まったく。僕は首を振り、その問題はとりあえずあとに回すことにした。そもそも常識が通用するような男ではないのだ。そんなことは始めから分かっていたではないか。それでひとまず次の問題に移ることにした。
「それで、その腕のタオルは何なんだ?」
「そう、これなんだ」と彼はひどく痛そうな顔つきをして言った。「実は肘を痛めてしまった。それで保冷剤を借りに君の部屋に来たんだ。俺のところにはそんなものないからな」
そのとき気付いたのだが、たしかにタオルを巻いた肘の部分が四角く出っ張っていた。その光景はいつかテレビで見た降板直後のプロ野球のピッチャーみたいだった。
「何でそんなことに?」と僕は訊いたが、彼はぶつぶつと独り言をつぶやいていた。
「まったく、ついこのあいだも十五日間の故障者リストに入ったばかりだったのに・・・」
「故障者リスト?」と僕は驚いて言った。
「そうだ」と彼は言った。「どうやら俺の持病らしい。パソコンのキーボードを打つたびに鋭い痛みが走るんだ。この間も痛みがやってきて、十五日間マイナーリーグで調整する羽目になった」
マイナーリーグ? 彼は何のことを言っているのだろう? でもどうも話が長くなりそうなので、そこを突っ込むのはやめておいた。とりあえずは今のことに話を戻さなくてはならない。
「そんなに悪いのか? つまり詩も書けないくらいに」
彼は神妙な顔つきで頷いた。そしてタオルの上から肘をさすった。
「駄目だ」と彼は言った。「これはどうやら手術の必要がありそうだ。トミー・ジョン手術だ。腱を別の部分から移植するんだよ。どうやらこれから一年は棒に振ることになるだろうな」
「そんなに?」と僕は驚いて言った。野球のピッチャーならともかく、どうして作家志望の人間が一年も棒に振る必要があるのか?
「書くということは」と彼は僕の心を読んだように言った。「それくらいエネルギーを必要とすることなんだよ」
彼はこれからの計画を話してくれた。「なあ、俺がこうして肘を壊してしまった以上、その間の執筆は君に任せるしかない。というのも俺の詩的霊感は今冴えわたっているからだ。しかしこのように物理的な要因によって、それを形あるものにすることができない。となると誰か信用できる人間に代わりに書いてもらうしかないんだ」
「そしてそれが僕だと」と僕は言った。
「そうだ」と彼は言ってまた肘を――というか保冷剤を――さすった。
「それで」と僕は言った。「一体いつからそれを始めるんだ?」
「今からだ」と彼は言った。そしてまっすぐ僕の目を見た。「決まってるじゃないか」
僕らは場所を彼の部屋に移し――といっても同じマンションのすぐ隣の部屋に移動するだけなのだが――彼の部屋のパソコンを起動した。周囲に物は少なく、ひどくがらんとした印象を受ける。何冊かの本が隅の方に散らばっていたが、どれも僕が聞いたこともないような作家のものばかりだった。中には何語かまったく分からないものもある。それを見ていると僕はちょっと不安になってしまった。果たしてこれは本当にこの地球上の言語なのだろうか?
「これは神田の古本屋街で買ったんだ」と彼は説明してくれた。
さて、ワープロソフトを起動したはいいものの、彼は特にこれといった指示を与えるわけでもなく、僕の背後に椅子を置いて、ただそこに座ったままでいた。そしてじっと白紙の画面を睨んでいる。
「それで?」と僕は待ち切れずに言った。「一体何を書けばいいんだ?」
「ちょっと待って」と彼は言った。「今意識を集中しているから」
「オーケー」と僕は言った。
そのまましばらく時間が経った。部屋の中はほとんど何の音もしなかった。かなり低い温度に設定されているエアコンの唸りだけが、静かに鳴り続けていた。僕はできるだけ彼の方を振り向かないように、その集中力を乱さないように、ということを考えていたのだが、さすがにこうも時間がかかってはそろそろ心配になってきた。
「大丈夫かい?」と言って、僕はゆっくりと彼の方を振り返った。
するとそこにあったのは意外な光景だった。最初は眠っているのだと思った。でもよく見るとその目はほんの少しだけ開いている。聞こえるか聞こえないか、という程度の本当に小さな音を発しながら、彼は呼吸を続けている。肘の保冷剤がずれかかっていたが、今彼はそんなことは一切気にしていなかった。彼が気にしているのは、何か別のことだった。
そのとき突然、彼は無事な方の左手をすっと伸ばし、僕の肩に触った。それはすごく自然な動作だった。まったく作為的ではない。その手は僕に何かを伝えているように思えた。何かとても大事なことだ。おそらく言語以前のことだ。僕はとっさに前を向き、そこにある白紙の画面と向き合った。彼は今何かを言おうとしている。僕はそれを聞き取り、文章という形に移し替えなければならない。
意識を集中すると、水の滴るような音が聞こえてきた。ポトリ、ポトリ、とそれは鳴っていた。しかしそれはたとえば台所で水が垂れているとか、そういうことではなかった。その音が鳴っているのは、どこかずっと遠い場所だった。本能的にそれが分かった。僕はそこに意識を集中し、何が起こるのかを書きとめていく。白紙の画面に新たな文章が生み出されていく・・・。
「空白 2」へと続く